会員関連資料
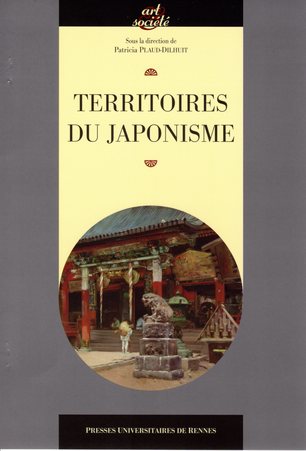
TERRITOIRES DU JAPONISME / ジャポニスムの諸領域
紹介: 伊藤史湖 会員 (久米美術館学芸員)
2014年12月
この度、レンヌ大学出版局(Presses Universitaires de Rennes)より、TERRITOIRES DU JAPONISME という書籍が刊行されました。この書籍は、遡ること2年前に同大学で行われたシンポジウムの発表を活字化したものです。
レンヌ大学出版局: TERRITOIRES DU JAPONISME
![]()
2012年、ブルターニュでは、「ブルターニュ日本2012年」と題して、美や食、健康など多岐にわたる様々な文化行事が行われましたが、その中心となったのが、ブルターニュ各地の美術館において開催された日本美術やジャポニスムをテーマとした14からなる展覧会でした。シンポジウム "Territoires du japonisme" (ジャポニスムの諸領域) は、その一環として9月27〜29日の3日間、レンヌ第2大学にて行われました。
発表者はフランス人と日本人研究者を中心に19人から成り、ジャポニスムに関係した様々な視点からなるテーマが掲げられました。
本記事筆者の伊藤もその一員として「ブルターニュを描いた画家久米桂一郎とその他の日本人画家達」と題して発表しました。これは、ジャポニスムとはむしろ逆に、日本人がフランスの影響を受けた事象ということになりますが、本シンポジウム開催委員のお一人の三浦篤東京大学大学院教授から、「ブルターニュを訪れた日本人画家については、フランス人にはあまり知られていない事実なので、この機会に紹介をしてみては」というご提言をいただいたことが契機となって発表に至ったものです。
発表内容は、ブレア島における久米の行動や交友関係について、伊藤がかつて数回にわたり実地を調査したものを、当時の資料と併せて報告するというものでした。また、久米が黒田清輝とともに最初にブルターニュを訪れたのは1891(明治24)年ですが、これは現地で制作した最初の日本人画家と考えられますので、彼ら以降、大正期頃までに時代を絞って、その間にブルターニュに赴いて作品を描いた主な日本人画家、鹿子木孟郎、坂本繁二郎、山本鼎などを、その作品と共に取り上げました。
多くの日本人画家がそれぞれの形でブルターニュに魅せられ、その風景や風俗を描き表 したことは、シンポジウム出席者の方々に新鮮に映っただけでなく、発表者伊藤にとっても同様に新たな視点の発見となりました。
そしてこの度、このシンポジウムは、レンヌ第2大学 Patricia Plaud-Dilhuit シンポジウム実行委員長の監修・編集のもと活字化されて、TERRITOIRES DU JAPONISME (ジャポニスムの諸領域) として、刊行に至りました。本書刊行を機会として、今後はブルターニュを訪れた日本人画家たちの展覧会の開催へとつなげていきたいと考えています。
伊藤史湖

久米桂一郎 黒田清輝とともに歩んだ僚友
モアンヌ・前田恵美子
対談: 伊藤史湖 会員 (久米美術館学芸員)
L' association Artistes du Bout du Monde の協会誌 Artistes du Bout du Monde Cahier No8 2012年秋号に掲載された記事。
同協会は、黒田清輝がフランス留学中に滞在し、多くの秀作を残したグレー村で活動する団体です。
日本語抄訳
2010年12月の記事「グレー・シュル・ロワンの芸術家コロニー」の中に、黒田清輝を語る際に避けては通ることのできない仲間・久米桂一郎の作品を紹介する機会を得た。
今回は、黒田との関係、二人の芸術家がどのようにお互いを補い合って活動したのか、などについてお伝えしたい。久米美術館・学芸員の伊藤史湖氏に取材した。
挿画キャプション
「少女」久米美術館
黒田清輝と久米桂一郎の交遊は、1886年パリで出会った20才の時から1924年に黒田が没するまで、無比の友人として続きますが、これほど迄深く二人を結びつけたものは何だったのでしょうか?
二人は同じ年生まれで、出身も共に九州の藩士の家庭という似た環境で育ちながらも、正反対ともいえる性格がお互いを補っていたことが、二人を深く結びつけた直接の要因といえます。しかしそれ以上に、美術に対する理念や姿勢が一致していたことが、生涯にわたって交友が続いた一番大きな理由だと思います。
久米桂一郎の生い立ちは?どのような父親のもと育てられたのでしょうか?
久米桂一郎は、佐賀藩主鍋島直正の近習を務めていた久米邦武の長男として、佐賀城下で生まれました。父の邦武は、明治維新後、藩校弘道館の教諭を務め、1871年(明治4年)には特命全権大使岩倉具視に随行して1年10ヶ月にわたり欧米を視察、帰国後、報告書『米欧回覧実記』を編集・執筆します。1888年(明治21年)帝国大学文科大学教授に就任、1899年(明治32年)からは旧友大隈重信の東京専門学校(現在の早稲田大学)で教鞭を執りつつ、歴史研究の論文の執筆をはじめとして多方面にわたる研究に専念しました。
法律志望から画家に転向した黒田と異なり、最初から画家をめざしてパリへ留学した久米の動機は何だったのでしょうか?
久米は、塗り絵をしてよく遊んだこと、父の西洋土産の中に西洋の絵画があったことなどが幼い頃の記憶として残っている、と自ら語っています。そして展覧会を子供の頃から強い関心を持って見学しました。1881年(明治14年)の第二回内国勧業博覧会に出品されていたコンテ画を見て、西洋画家を志すことを決意し、まず日本で西洋画の学習を始めます。
パリへの留学の動機ですが、当時としてはまだめずらしいことですが、父親はじめ親戚や親近者の中に西洋に渡航する人が少なからずいたので、自身も同じような体験をしたいと思っていたのかもしれません。そして最終的、決定的な動機としては、日本での西洋画の師であった藤雅三がパリに留学することになったことが挙げられるでしょう。
挿画キャプション
「フランス風景:ブレア島」久米美術館
「林檎拾い」 1892年 久米美術館
父、久米邦武は明治政府の使節団に随行し、『米欧回覧実記』という報告書を執筆していますが、父からの影響はどのような所に現れているでしょうか?
西洋見聞実録である『米欧回覧実記』(全5冊)は、訪問した各国の総論から、具体的な文物まで、細かく述べられています。その構成や内容は、理論的で科学的、実証主義的ともいえます。桂一郎の美術啓蒙家、美術評論家としてのスタンスは、この父親譲りのものと考えられます。
また父・邦武は、豊富な知識・学識に加え、ビジネス感覚も備えていたので起業や投資等にも興味を示し、学者の域にとどまらない活躍をしました。例えば、開国後、海外との貿易を重視して、陶磁器を日本の産業を支えるひとつと見なし、会社組織発足を郷里の知人たちに促し、組織をオーガナイズするとともに、ブレーンとして組織の活動をフォローします。また、維新後衰退していた能楽が、日本の外交や国民の娯楽として不可欠である、とその必要性を唱えて岩倉具視らとともに能楽再興の運動を起こします。このように、邦武は、いわばプロデューサー、知的顧問、オーガナイザーのような役割を多岐のジャンルに渡り果たしました。
久米が常に黒田の背後にいて、表舞台には出なかったのは、このような父の血を引き、かつ父親を見本として育ったところにあるとも推察できます。
挿画キャプション
「裸婦習作」久米美術館
帰国後、桂一郎について『半西洋人なり』と言っていた父との関係は?
久米と黒田は1893年(明治26年)、ほぼ同時に帰国しますが、二人は、フランスでの生活をそのまま日本に持ち帰りました。二人の身なりは、当時としては日本の人々にかなり奇抜に写ったようです。帰国間もない息子桂一郎を「半西洋人なり」と言って父邦武が敬遠したのは、おそらく、こういう部分だったと考えられます。
しかし、久米と黒田の二人が帰国後に挑んだ当時の日本における西洋美術の改革には邦武は大いに理解を示し協力的でした。帰国後の翌年に二人が開設した画塾「天真道場」という名前も邦武の命名によります。また、その後仲間たちと結成した新しいスタイルの美術団体「白馬会」が発行した雑誌『光風』創刊号には邦武が「序文」も寄せています。
色々な人々が邦武に意見を仰いだのと同様、二人も行動の要所要所で父から助言を得ていたであろうことは明白です。
フランスでの生活はどのようなものだったのでしょうか?
1886年の8月末、久米はパリに到着するとただちに日本での西洋画の先生であった藤雅三を訪ね、アカデミー・コラロッシに教室を持つラファエル・コランへの紹介を受けます。一方、黒田は1884年に法律を学ぶためにパリにやってきますが、美術に専念することを決心し、コランに入門したのは、その矢先のことでした。
久米と黒田は、夏休みの明けた9月にコランの教室で出合いますが、すぐに意気投合します。アパートも二人でシェアし、毎日昼はコランの教室に、夜は夜間学校にと、ともに美術の学習に励みます。他の日本人留学生や海外からの美術学生との交友も盛んになり、学生らしい楽しい日々を送りました。
学習は、はじめ教室での裸体デッサンが主でしたが、次第に郊外に出てスケッチ旅行も行います。グレーに初めて黒田とともに訪れたのは1890年のことです。ウォルター・グリフィン、クラレンス・バードなど、外国人画家たちとの交流も盛んになりました。
ラファエル・コランが1916年に亡くなった際、師の芸術性について「先生はどこまでもクラシック派の代表者であって...特にギリシャ思想の高尚なるところを狙っておられた」「デッサンの純正なことを主眼とした技術であるからして、フランスのごく正統なる伝習を保存していく側」と追憶しています。モネやルノアールといった印象派の画家たちと同時代に生きながら、その流行に傾倒せず、地道に自身の芸術を貫いたコランの生き方をも久米は尊敬していました。また、日本美術を愛したコランのために、久米・黒田はそれぞれに、反物や古い能面といった工芸品を日本から調達しています。
1888年、なぜ始めたばかりの絵の勉強を中断してまで、バルセロナ万博のために1年も滞在し、孤軍奮闘しなければならなかったのでしょうか?
バルセロナ万博で日本政府から出品物を一括託されていたのが起立工商会社という会社で、その社長の松尾儀助は、佐賀出身で父邦武の親しい知人でした。バルセロナ万博は予算や日本からの地理的な関係から携わる人も限られていたので、パリにいる久米はちょうどよい人材でした。手伝いにバルセロナへ向かうことになったのは父親の命によるものです。久米のフランス留学は私費であり、父親から援助を受ける立場でしたし、当時の時代背景を考えても父親の命に背くことはできなかったのでしょう。
一方、スペインというフランスとは異なる地への好奇心もあったと思われますし、さらには、美術学生として、スペインの本場の絵画も実際に触れたいという向学心もあったと考えられます。久米はバルセロナ滞在中も絵を描くことはおろそかにしなかったようですし、万博の仕事が終了すると、マドリッドやコルドバ、グラナダ、セビリアなどを約1ヶ月かけて周り、スペイン絵画を数多く鑑賞したほか、自らも風景のスケッチや名品の模写をしています。
また、バルセロナ滞在中に親しく交友したアントニオ・ガルシア・リヤンソは、バルセロナの美術評論家・歴史学者で、久米に多大な影響を与えました。リヤンソは日本に強い関心をもっていたところから久米との交友が始まったと推測されます。ほぼ毎日のように家族ぐるみの付き合いをしており、西洋美術や歴史について学ぶところが多かったと思われます。リヤンソは久米に欧州の旅行を勧めたりしました。リヤンソとの深い知的交流は少なからず留学1年生の久米には多大な影響を及ぼしたことでしょう。また一方、久米はリヤンソに日本について語りました。外国の知識人に話し伝えることで、久米の日本美術・文化への認識もあらためられたと考えられます。ちなみにリヤンソは後年、日本についての著作DAI NIPONを出版し、その謝辞には久米の名前を挙げています。
挿図キャプション
「フランス風景:グレー」 久米美術館
「夕潮:ブレア島」 久米美術館
「寒林枯葉」 東京芸術大学美術館
ウィーン万博を1873年に視察した父の邦武は、万博を「平和時の戦争」と言い切っていますが、生涯万博に携わることになる桂一郎も、同じように考えていたのでしょうか?
1888年、黒田がコランのもとで絵画学習に没頭している時、久米はバルセロナ万博の会場にいました。もともと事務的なことに長けていた久米は、荷解きから販売までのあらゆる雑務をこなし、出品予定の陶磁器の出来が平凡とみると、自らの陶磁器の置物を出品して金牌を受賞したりもしています。続く1889年のパリ万博では通訳として働きました。
久米が生涯にわたり博覧会事務に携わることになったのは、本来の「事務的能力」に加え、海外をよく知り、かつ美術に精通している適任者が他にまだ少なかった、というのが大きな理由だと考えられます。
久米は父親のように万博を「太平の戦争」とのみ捉えていたのではなかったと思います。むしろ、「各国の最新の美術事情を確認する場」と捉えていたのだと考えます。この違いは、父邦武の時代、すなわち日本が西洋に追いつくにはどうしたらよいのかを手探りで捉えようとした時代と次の世代との相違であるともいえます。
久米はサロン入選を目指して、留学最後の仕上げにブルターニュのブレア島に一人で長期滞在していますが、なぜブレア島を選んだのでしょうか?
黒田がグレーという、絵画制作における「絶対的な」場所を見いだし、魅力的な作品を次々に制作していったことは、おそらく久米にとってうらやましいことであり、また、焦燥感もありました。ちょうどその時、ブレア島のことを知りました。久米は、自らの作品を表現できる場所を見つけるべく、1891年(明治24年)に、そして1892年にも8月2日から翌年1月までブレハ島に滞在しました。
ここで、描いた「秋陽海村に昇る」と「夕潮」は1892年のサロンに提出され、また、現在久米美術館に収蔵されている「林檎拾い」と「晩秋」も1893年のサロンに出すべく描かれました。残念なことにいずれの作品も入選することはありませんでした。また、大作ではありませんが、同じくブレア島を描いた「フランス風景」も明るく伸びやかな作品として久米の代表作と言われています。グレーで描いた「寒林枯葉」も代表作のひとつです。
ブレア島も当時は芸術家のコロニーの一つでしたが、どのような画家がいたのでしょうか?グレーに滞在した画家もいますか?
芸術家たちがこの島に注目するようになったのは、1890年頃で、その中心人物は、1889年パリ万博で銀賞を受賞したスウェーデン人画家アラン・オステルリン(1855〜1938)や、著名な思想家・宗教学者アーネスト・ルナンの息子でP.シャヴァンヌに師事したアリィ・ルナン(1857〜1900)などです。ウォルター・グリフィンもブレア島に滞在していました。画家たちは酒場に集り、各々使用するグラスにお互い絵を描き合い、自分の顔のグラスで酒を飲んでいました。久米の肖像のグラスは、ジョルジュ・ランデル(1860〜1898)という画家が描き、現在も残っています。この風習は、1930年代半ばまで続き、現在200近いグラスのコレクションを見ることができます。これらはブレア島の歴史を物語る貴重な資料ともなっています。
写真キャプション
様々な国籍の芸術家たちの交流
アメリカ人ウォルター・グリフィン、クラレンス・バード、久米桂一郎、黒田清輝
帰国後も、日本におけるアカデミックな洋画教育の基礎作りのために黒田と常に行動を共にし、「黒田と久米」、と常に並置されていた久米ですが、次第に黒田のみが近代美術の画家と呼ばれるようになり、久米の名は黒田の背後に隠れるようになったのはなぜでしょうか?
1893年に日本に戻った久米と黒田は、翌年に画塾「天真道場」を開き、後進の指導を始めます。それは、日本においてそれまで主流であった西洋画とはまったく異なる、光を取り入れた明るく清新な画風でした。フランスで培った最新の学習方法とともに、制作に対する自由な姿勢も含めて、たちまちに若い画学生たちを魅了しました。また一般にも広く支持されて、彼らのグループは一躍日本における西洋画の主流となり、1896年の新しい美術団体「白馬会」への結成へと繋がります。
さて、久米が画家として名前が残らなかった理由として、黒田が作品を描き、久米は作品ではなく理論面、すなわち美術史や考古学、美術解剖学などを教える、という役割分担が確立されていったことによります。役割分担が明確になったのは「裸体画事件」が起きた時です。1895年(明治28年)に京都で開催された内国勧業博覧会において、黒田の「朝妝」という裸体画が展示されますが、これが社会的に不適切であると非難された事件です。この時、久米は論文を発表して、西洋美術における裸体画の意義を主張して黒田を擁護しました。そしてこの裸体画事件は、自分の適性はむしろ理論的バックアップであるとはっきりと認識し始めた出来事だったと考えられます。
裸体画問題以来、画家黒田を援護射撃するため執筆活動が盛んになりますが、絵を描かなくなったのはいつ頃の事でしょうか?
1896年西洋画科が新設された東京美術学校で、黒田と久米は教授の職に就きます。久米はここで、考古学と美術解剖学を担当します。黒田の絵を描く才能を認めただけでなく、画家としての自分の限界も感じ始めたのはこの時期でした。一方自分の適性は、理論面でのバックアップであることをはっきりと認識したのです。1897年に裸体画問題が再燃すると、久米は再び理論を以って黒田を擁護しました。
1899年(明治32年)頃を境に久米は絵画制作を止め、もっぱら美術啓蒙や海外の展覧会事務などの活動に励むことになります。様々な専門書を入手し、それらをもとにして西洋美術を紹介する論文や翻訳を数多く発表します。フランスで入手した書籍も、美術の専門書にとどまらず、歴史・神話・文学など多岐の分野にわたっています。西洋美術の理解、ひいてはその制作においては、広い分野の知識が不可欠であることを久米は留学の早い時期から理解し、かつ、それを重視していたということが判ります。
このように久米は黒田の活動を常に助け、知識面でフォローする役割を果たしました。黒田の没後も自らの生涯を閉じるまでの10年の間、日本の美術の近代化を進めた友人に敬意を払いながら、啓蒙活動を続けました。
今二人が再び顔を合わしたら一体何というでしょうか?
「あの時代に戻ってもう一度パリで暮らしたいね。」
結び
フランスで学んだ近代的な方法をもって、西洋美術の教育や啓蒙という役割を久米は黒田の傍らで果たしてきました。黒田は、このような久米の後ろだてのもと、生涯を通して絵画にすべてを捧げることができたのです。長い間、黒田の陰に隠れていた久米の評価をする時が来たといっていいでしょう。

